
名前について
役者をやっていると、自分以外の名前で呼ばれることが多くなる。
演技中だけじゃなく、出番を呼ばれる時も役名の方が多いので、青沼だろうが占部だろうが、その役をやっている期間は、自動的にその名前に反応して振り向く。町で知らない人に呼ばれたとしても、きっと振リ向く。
言ってみれば、マラソン大会でもらったゼッケンみたいなものだとは思うが、面白いのは、青沼という名前になったら、なんとなく青沼という人の気分にもなることだ。「青沼気分」ってどんな気分だよとちょっと笑ってしまうが、そこには確かになにかの気分があって、ゼッケンではならないのだから、名前というのはやっぱり記号とは違うのだと思う。
『カエアンの聖衣』というSF小説があって、そこに出てくる宇宙人たちは「服は人なり」という哲学を持っていて、服によって人格が変質したりもして、まさに「服に着られてしまう」のだが、名前もそれにちょっと似たところがあるように思う。
華やかな服を着れば華やかな気分になり、パンクな服を着ればパンクな気分になるように、名前にもそれにあった気分があって、その名前に支配されるというか、影響される面があると思う。
たとえば虎ノ助という名前だったら、呼び捨てだったり「虎ちゃん」だったりと、皆がどこか親しみを持って呼ぶから、どうしても愛嬌があってオープンな性格の子に育つような気がする。名前が持つやんちゃなイメージに影響されるせいで、理系の神経質な子にはならない気がするのだ。
初対面の人と会うと、僕らはすぐに名前を聞こうとする。何をやっている人かなどより名前を知らない方が不安であるかのように。なぜかよくわからないが、名前を聞くと、なんとなくその人を知ったような、ほっとするところがあるのではと思う。本当はその人のことを知らないはずなのに、名前を聞いただけで安心してしまうのなら、もしかしたら、名前は時にはその人を本当に知るのに邪魔になる可能性まである。
あだ名というか、呼ばれ方で、相手が自分にどんな印象を持っているかもわかる。
僕も、剛、剛ちゃん、利重さん、りーさん、などと、いろいろな呼ばれ方をする。その呼び方の中にある感情が面白い。だから、正式な名前なんかいらなくて、みんな勝手に好きな名前で呼んでくれたらいいのにと思うことがある。そしてその名前で呼ばれたら、僕はその人といる間はその名前の人になるのだと思う。
名前を持たず、いつしか神様と呼ばれてしまった男の話をいつか必ず書いてみたいと思っている。
かつて19世紀のドイツに実在したカスパー・ハウザーという不思議な人物のように、生まれた時から何者かに監禁され、名前も言葉も持たないまま育てられ、ある時急に町に放り出された男の話で、本籍も名前も持たないままに、町の親切な人たちに保護され、日雇いの仕事などを貰いながら生きてきた男で、皆が思い思いの名前で彼を呼んでいる。だからあんたも好きな名前で呼んでくれと、ある日偶然知り合った新人女性ライターは彼に言われるが、自分が感じた印象が相手にバレてしまうのを恐れてすぐに名前をつけられない。しかし彼にとても興味を持つった彼女は、彼を取材していくうち、皆が、彼の持つ不思議な愛嬌に心を許し、なんでも話す光景を見て、どこか街角のカウンセラーのようだと記事を書く。その記事が反響を呼び、急に人が集まり始め、宗教のように崇められ祭りあげられた彼は、持ちたくもない名前をいつの間にか持たされて、挙句は『名無しの神様』とまで呼ばれ、本人の意思とは関係なく時代の寵児に持ち上げられ、ピークになったところで今度は逆に落とされていく。1980年のある新宿の酒場から始まる、40年にも渡る壮大な波乱万丈の物語だ。その物語の中で、僕は、名前というものが持つ力についての考察を、思う存分書いてみたいと思っている。
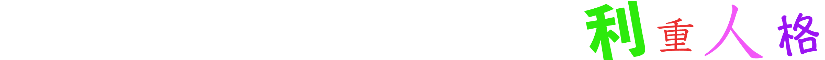
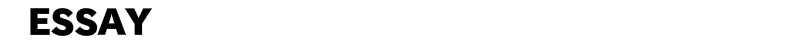
 前のページへ
前のページへ