
夜の色
昼間があまりに暑いから、当面、散歩は夜にすることにした。
日が落ちてもう2時間になるというのに、熱気は当り前のような顔をして居座っていて、外に出た瞬間、草いきれが強く鼻をついた。でも、決してそれは嫌な感じばかりではなく、土の存在を感じさせてくれ、自分が星の上に住んでいるのだと改めて感じさせてくれた。
ギラギラした街の方には行きたくなかったので、細い道を縫うようにゆっくりと歩いた。ゆるやかな坂を上りきったところで振り返ると、家々の灯りが見渡せた。
ふと、「変わったなあ」と思った。だけど、それはなんの変哲も無い日本の住宅街だったから、何がそう感じさせるのかわからず、ちょっとの間考えた。
灯りだと思った。家やマンションの窓からもれてくる灯りの色が、昔に比べて、暖かい色が増えているのだと思った。
僕は高度経済成長時代に育ったけれど、それは「蛍光灯の時代」でもあったように思う。裸電球よりはるかに経済的で明るいと言われ、新しく建っていく団地の窓から見える光はみんな蛍光灯だった。街灯も次々に裸電球から蛍光灯に変わっていき、いつしか普通の家も蛍光灯が当たり前になり、日本中はすっかり蛍光灯の国に変わった。
だけど、僕はその青白い光が好きじゃなかった。みんなが言うように明るくてきれいで目にも良いのかもしれないけれど、蛍光灯に照らされる物や人は、みんなポツンと寂しく見えた。遠く見える団地の灯りを見ていると、なんだかいつも寂しい気持ちになった。そのひとつひとつの灯りの中にはたくさんの家族が住んでいるのに、イメージの中では、誰もいない部屋でただ物だけが照らされていたり、食卓を囲んでいる家族が皆動かない人形だったりというようなシュールなイメージを感じたりしていた。裸電球というのも感傷的な寂しさがあるけれど、そのフォルムの可愛らしさもあってどこか人間味を感じる。それに対して蛍光灯の光は、寂しさを越えて「孤独」を僕に感じさせた。電球は人恋しさを照らし出し、蛍光灯は孤独を照らし出しているように感じた。帰りたい家の灯りじゃなかった。経済は成長したけれど、殺伐とした事件が多くなったのも、実は蛍光灯のせいなんじゃないかと、ひそかに思うこともあった。
時代は変わって、今やLEDになった。ひとつの電球で昼光色から電球色まで変えられる天井灯なんてものが出てきたおかげで、また何かが変わってきたんじゃないかと思う。選べるなら、青白い光よりオレンジ色の光の方が気持ちが良いや、と感覚的に選ぶ人が増えはじめて、夜の色が徐々に変わってきているんじゃないだろうか。今、遠くに見えるマンションの窓からもれる灯りは、半分以上がオレンジ色だ。アパートの通路の灯りさえも、暖色が増えてきていることに気づく。面白いなと思う。たったそれだけで、景色は変わっていくのだ。ということは、たとえば映画やドラマで、夜景を一瞬映すだけで時代感を出すこともできたりするのだなと思う。
オレンジ色の光は、火を連想させる。みんなが集まってくる焚き火の色だ。そこには人がいる、と暖かい気持ちにしてくれる。
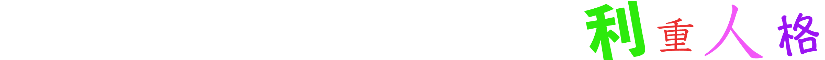
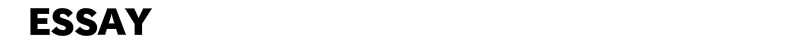
 前のページへ
前のページへ