
岡本喜八監督・命懸けの軽さ
『反骨精神』という言葉をあまり聞かなくなったように思う。
『自由』という言葉は相変わらず大安売りだけれども、意味が少しずつ変わってきているような気もして、「自由度が高い」なんて売り文句があちらこちらに踊っていたりするのを見ると、近頃は、与えられた範囲の中で許されている部分のことを、自由と言うのかしらん? と首を傾げたくなる時がある。
岡本喜八カントクの映画は、まさに『自由』と『反骨』そのものだ。
カントクの映画は、どれもこれも自由奔放で、「え、こんなことやっちゃって良いんだ?」とびっくりさせられることだらけ。
え、行進している兵隊さん達が、急にミュージカルみたいに歌い出しちゃっても良いんだ?
物語の途中で急に解説が入っちゃったり、アニメになっちゃうのって、ありなんだ?
映画の最初に終マークが出ちゃったり、思いだしたようにタイトルがもう一度出て来ちゃっても良いんだ?
ジャズもロックも和楽も、一本の映画に全部ぶち込んじゃっても全然大丈夫なんだ?
喜八映画の洗礼を受けると、いつの間にか「こうあるもの」と勝手に思っていた自分の頭の狭さを思い知らされる。そして、とてつもなく愉快な、わくわくした気持ちにさせられる。
映画って、そもそも自由なものだろ? だから映画が好きなんじゃないのかい? 映画なんて、たかだか百年ちょっとの歴史しかないんだから、まだまだ新しくなっていいはずだ。「映画とは……」なんてもっともらしい顔で講釈垂れるような奴等を信用するな。そんなのを相手にするヒマがあったら、先に行こうぜ。ジャンルという分け方なんか、誰かが後で勝手にやればいい。大事なことは「面白い」ってことだ。こだわるのは、そこだろ?と、カントクがスクリーンの向こうからウインクしている。
だから、カントクの映画は、ひたすら面白い。ただただ面白い。だけども、見終わった後、「あー、面白かった」と思うだけですぐ内容を忘れちゃうような映画じゃなくて、むしろ、むくむくといろんなことを考えたくなる映画なのだ。そこで初めて、映画が持っていた強烈なリアルとメッセージを感じることになる。それこそ岡本喜八映画の真骨頂だと思う。
カントクの映画は、一見、パズルのような作り方をしているくせに、映画のスクリーンから飛び出て強烈に迫ってくるのはいつも、どんなに踏みつけられてもへこたれない、雑草のような人間達の逞しいエネルギーだ。
カントクの映画は、誰もが平等に脇役だ。脇役だと思われている人間こそが主役なのだと、カントクの映画は証明して見せる。そして、自分を大物だとか主役だとか勘違いしている人間達を、徹底的にこき下ろして笑い飛ばす。
権威だとか権力だとか、こうするべきだとか、エラソウなものには、生涯、徹底して反逆した。だけどヒステリックになんかじゃなく、あくまでも軽く、かるーく反逆した。自分がエラソウになるのも、生涯、拒否した。ひょい、ひょい、ひょい、と、軽妙に生ききった。
だけどその軽さは、筋金入りの軽さだ。実際に戦争を体験し、エラソウなもののために死んでいった沢山の人を見てきた人から出てくるからこその、凄みのある軽さだ。いわば、命懸けの軽さなのだと思う。この軽さは誰にも奪わせない。そんな覚悟を感じたりする。
カントクは、自らの作る映画そのもののように、飄々として、スタイリッシュで、ユーモラスで、シャイで、カッコイイ人だった。
カントクの現場にいるのは、至福だった。メガネの奥から悪戯っ子のような目で見てくれている感じが、自分も悪戯の共犯者にしてもらっているようで、嬉しくて嬉しくてしかたなかった。
亡くなる前にカントクに見せていただいた新作のシナリオは、とても八十歳の人が書いたとは思えない、「これ、いったいどうやって撮るの?」と言いたくなるような、エネルギッシュでアバンギャルドなものだった。宇宙人も出てくれば幽霊も出てくる、とにかくなんでもありの、ありとあらゆるものを詰め込んだ、まるで自由のかんしゃく玉のような映画だった。
「また、久しぶりに、ひんしゅくを買うもの、やろうと思って」
そう言って、へへへと笑ったあの表情が忘れられない。
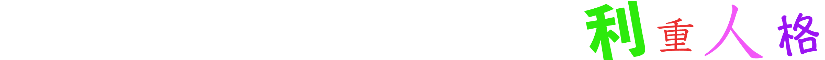
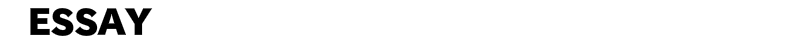
 前のページへ
前のページへ