
演技と『内なる目』
ニコラス・ハンフリーという動物行動学者が書いた『内なる目 意識の進化論』という、すこぶる面白い本がある。人はなぜ自己意識を持つようになったのかについて書かれた本だ。自然界には理由のないものはほとんど何も存在しないことをダーウィンの進化論は示唆しているけれど、それなら、心はいったい何のためにあるのか?心はなぜほかの形ではなく、こういう形で進化してきたのか? これについてハンフリーは実に魅力的な仮説を示している。
およそ600万年前に、類人猿の1グループが、森にとどまらずに草原に進出したと思われる。これが大きな分岐点だとハンフリーは言う。サバンナは森より危険が多く、肉食動物から身を守りながら逆に狩猟するためには彼らは集団でいる必要があり、生き延びるために社会的な知能を発達させる必要があった。それに加えて、とても大きな要因として、他の類人猿グループと遭遇した時に、争わずに交流していくことが、生き延びるために不可欠だったという。
そのためには、遭遇した相手の行動の意味を知る必要があった。なぜ歯をむき出しているのか、なぜじっとこちらを見つめて動かないのか、それを知るための手がかりは、自分の中にしかなかった。同じ行動を模倣してみて、その時の自分の状態を観察し、そこから相手の感情を類推する必要があったのだという。そこに意識の発達があった。意識というのは自己認識のことで、僕たちが直接知りうる唯一の意識は、自分の意識だけだ。僕たちが他の人に心を見る時、僕たち自身が投影したものだけを見ている。
群れで生きる動物は、他にも沢山いるけれども、類人猿だけが必要以上にさえ見える大きい脳を持っているのは、その頭脳をお互い同士の関係を処理する時に、その極限まで使っているからだ。本能に従って自動的に反応しているだけでは人類は生き延びることができなかった。この600万年の間、他の人間の心を読むことが、人類に課せられた重い務めだった。他の人の立場に身を置く能力が必要だった。そのために、自分の心をあらゆる事物の物差しとするという能力を獲得した。そこに「内なる目」、つまり「心」の発達があったのだという。
かなりざっくり要約すると、こういう内容なのだが、この本は他にもいろいろな考察が書かれていて、たとえば、映画や演劇というものが生まれたのは、カタルシスのための娯楽と思われがちだが、他の人の感情を自分のことのように擬似体験をするという「内なる目」のそもそもの目的を考えれば「必然」だったろうと示唆していたり、戦争の際に躊躇なく敵を倒すことができるように、兵士に対して「内なる目」を外して自動的に服従するように訓練をしていることなどや、社会が膨れ上がりすぎた現代では、知らない人から教育されたり命令されることを当たり前に受け止めるようになって、社会を作るために必要だったはずの「内なる目」が逆に危機に陥りかけていることについても書かれていて、いろいろなことを考える刺激を与えてくれる本なので、興味がある方はぜひ図書館などで借りて読んでいただきたいが(古い本なので)、僕がこの本で興味深く思ったのは、これが「演技」を考えるヒントにもなっているなと感じたことだ。内なる目の発達は、実は「演技」というものの成り立ちそのものだと思ったのだ。
演技というのは、「自分ではない誰かとして振舞う」ことだ。そのためには「その人の気持ちになる」ことが大事になる。
役作りをする際、僕らはまず、脚本に書かれている行動や台詞から、その人物がどんな性格で何を考えているかを想像する。そして、書かれている以外の時間にも、その人物がどんな行動をしてどんなことを喋るのかまで想像して、その人間そのものになっていこうと試みる。その作業を進めるための手がかりは、なるほど、自分の心と照らし合わせることしかないのだ。自分の過去の体験から、似たような状況や感情はないか、引っ張り出してきて照らし合わせることから始めるわけだ。自分の心を探り、演じる人物と自分を擦り合わせる。まさに「内なる目」をフルに活用するのだ。
もうひとつ、かつて祖先がやったであろうことと同じく、形から入るアプローチもある。しっかり観察をして、その通りに真似をするところから入る方法。肩をいからせてアゴを上げ気味にガニ股で歩くと、どんな気分がするのか。人と目を合わさず相手の胸のあたりに視線を置いて喋る時は、どんな気持ちなのか。実際にやってみて、その時の自分の内面を観察すると、気づくことは面白いほど多い。気分が落ち込んでいる時に、わざと口角をあげて笑顔を作ると、その形につられて気分が朗らかになるという医学データもあるぐらいで、形を作ることで気持ちがついてくるということは確実にある。「形だけでやるな、気持ちから入れ」と言う指導者もいるけれど、実際には、自分の内面を探っていくアプローチと、形を真似るアプローチは、ふたつとも繋がっていて、どちらのルートからでもその感情にはたどり着けるはずなのだ。
こうして考えていくと、「演技」というものは、俳優がする特別なものではなく、人類にとって基本の能力そのものなのだとわかって、すごく面白い。
演技をすることは、誰にとっても大切なことなのだと思う。自分ではない誰かの気持ちを想像して、自分のことのように感じられること。そのためには自分を手がかりにすること。一見まったく理解不能のように思える人であっても、自分を探っていけば、きっと自分の中にその要素があって、その気持ちにたどり着くことができるだろうということ。
よく僕は、一人の人間の中に詰まっている感情は皆ほぼ一緒で、根暗とかネアカとかはなく、豪快だけの人も臆病だけの人もいなく、誰にもすべての要素があり、たまたまどれが表に見えているかの違いだけで、人はどんな人にでもなれると言っている。
そして、演技をいっぱいすることで、たくさんの立場の人の気持ちを知ることができれば、人に対してもっと優しくなっていけるはず。殺人犯や残虐な行動をする人に対して、「信じられない」と突き放すのではなく、自分の内面を探って、状況やタイミングさえ重なれば自分にもその気持ちが起こるのだとわかることで、人はもっと先に進める。誰もが実は自分と一緒なのだと思うこと。それが本当にきちんと想像できれば、そしてそのことをじっくりと話し合えれば、戦争などという愚行は避けられるはずなのだ。
映画や演劇ができることは、ここにあると思う。逆に言うと、見る人の「内なる目」を刺激しない演技は、何の意味もないと思う。
壮大な人類の歴史を想う時、「演技」というものが、生き延びるため、争わないための能力だったということが、僕をしみじみと感動させる。人類はその能力を思い切り伸ばして、時には他の動物や、果てはぬいぐるみのような生命の無い物体にまで感情移入ができるまでに進化したけれど、そもそもの理由はそこにあったのだ。「演技」=「騙す」というイメージもよく言われるし、確かにそういう面もあると思うけれど、それは進化の第二段階であって、それも成り立ちを遡って考えると、同調しているふりをしてみせることで争いを避けるという、サバイバルのために発達した能力だと思う。
つまり、演技とは、平和のための能力なのだ。
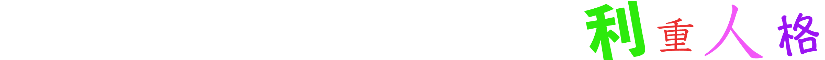
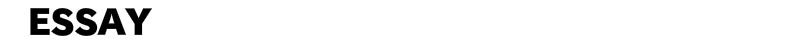
 前のページへ
前のページへ