
映画・想いのごった煮
映画を作るというのは、子どもを育てるようなもんかなあと思う。成績が(つまり客の入りがね)良いに越したことはないが、それよりまず味のある子になってほしい。全員に好かれなくても良いから、いろんな人と知り合って、その中で、何人かの大切な友達を持って欲しい。まあ、こう育てたはずだと思っていても、人から見ればそうではない場合もあるだろう(あるある)。だからといって怖がっていてはいけないから、勇気を持って育てる。願いを込めて。育っちゃったら後は、「ウチの子、どうですか? ホントはとっても優しい子なんですよ」などと出しゃばっちゃうのは死んでもしたくないから、ただただ信じて。どきどきと見守るのみである。
昔、面白いことがあった。
ある女の子が、どう調べたのか、僕の電話番号を突き止めて電話をかけてきたのである。
「突然電話をかけてくるなんて変なヤツだと思うでしょうけれど、私は純粋な『ZAZIE』(※僕の劇場用第一作)のファンなんです。見てすぐに一人で感想文を書いたんです。あれはすごい映画なんです」
「はあ」
それから彼女は、『ZAZIE』がいかにすごい映画で、いかに彼女にとって意味のある映画かということを、異様な迫力で僕に説明してくれるのだった。延々と喋りまくる彼女のあまりに熱心な言葉に対して僕はなんだか「ありがとう」というのも変な気がして、ただ、「そう、良かったね」とか「うん、うん」などと、人の好い親父のように相槌を打つばかりだった。で、ひとしきり喋りまくると彼女は急に、「でも利重さん、次の映画は作りづらいでしょうね」と言った。
「え、どうして? またすぐ作るつもりだよ。面白いものになると思うからさ、期待しててよ」と答えると、彼女は確信に満ちた声でこう言ったのだった。
「いやあ、『ZAZIE』よりすごい映画なんか、出来ないと思うな!」
僕は思わず吹き出してしまった。おいおい、じゃあ、いったいあの映画は誰が作ったんだ? つまり、僕の育てた子どもは、彼女と友達になるどころか、駆け落ちをしてしまったというわけである。
電話を切ってからもまだ大笑いしながら、僕は、“ああ、ようやくあの映画を終わらせることが出来たんだな”と、ほっとしていた。
編集、ダビングが終わってプリントが上がってしまえば、監督の出来る作業はそこで終わりである。つまり、完成だ。それまでの何ヶ月間の緊張が抜けた快いけだるさの中で初号の試写を見るのは、それはそれで充実感のある瞬間なのだが、それだけではまだ映画が本当に完成したことにはならないと、僕はいつも思うのだ。
映画は、劇場にかけられて人の目に触れた瞬間から、監督の手を離れ、一人歩きを始める。映画は勝手に観客とコミュニケーションを始める。人のフィルターを通って初めて映画は完成するのである。
それに気がついたのは、二十歳の時、16ミリ映画『見えない』を作った時だった。コミュニケーションをテーマにしたフェイクドキュメンタリーのその作品の上映期間中、僕はずっと劇場にいて、「そのへんをぶらぶらしているから気軽に声をかけてください」と言っておいたのだが、そのメッセージに応えて、実にいろいろな人が話しかけに来てくれた。彼らの話してくれた話のどれもが僕にとっては興味深く、また刺激的だった。ある人は、手をぐっと握りしめたまま見たと言い、またある人は、クスクス笑いっぱなしだったという。自分を振り返って重くなったという子もいれば、元気が出ましたという人もいる。感動した部分は千差万別、同じシーンでも人によって全然違うイメージのシーンになっていたりするのが興味深い。それぞれの人がそれぞれの思い込みで映画を完成させてくれている。不思議なもので、自分が描き足りなかったと思っている部分まで、見ている人は“感じて”くれていたりする。時には、作っている本人がまったく気にしていないカットに、その人はすごく重要な意味を感じて感動してくれていたりする。はなはだ無責任な話だが、その説明を聞きながら僕自身が「そうだったのか」なんて感動をしたこともあるぐらいだ。
そして彼らは、必ず最後には自分自身のことを話してくれた。
「あのね、ついこの間からドイツへ留学しようかなんて悩んでいたんですよ。でもね、今日、ここに来て偶然この映画見て、それが自分の逃げだって判りました。もうちょっと日本で頑張ってみます」
「俺は最近、工事現場でバイトしているんですよ。これが面白くてですね……」
感想と言っていいのかどうかわからないけれど、一番ショックだったのは、最終日に受付にあった置き手紙だった。ノートを破いたらしいその紙には鉛筆の走り書きで、「自殺、しません」と書いてあった。いや、僕は別に自分の映画を自慢したいのではない。そんなすごい映画を作った覚えはない。ちなみにその映画には「自殺」という台詞はひと言すら出てこない。「ドイツ留学は逃げだ」みたいな内容でも当然ない。新聞配送トラックの運転手である青年とたまたま知り合った僕がインタビュー形式で延々語り合っていくというだけの映画なのだ。自殺をやめた彼、もしくは彼女と、僕の映画の間にどんなコミュニケーションがあったのかは、わからない。ただ、一本の映画は、ある人にとっては、作った本人以上に大切なものになることもあるということだ。人間の想いというのはすごいものだなと思う。
映画は想いのごった煮だ。僕を始めとして何十人ものスタッフやキャストの様々な想いが詰め込まれる。想いを詰め込もうとすればするほど、足りない部分が出来る(だからこそ“想い”なのだが)。その、ものすごい数の未完成の想いのどれかが、見ている人の想いに引っかかり、共鳴し、映画は完成されてゆく。映画は人と話をする。手を握り合う。僕にもそういう映画がある。何本もの映画が僕を助けてくれた。
僕から始まった映画が、勝手に人と知り合い、仲良くなり、僕に紹介してくれる。そしてその人々は僕に生きてきた人生の一部を見せてくれる。こんなに幸福なコミュニケーションがあるだろうか。
僕は、自分の映画のロードショーの最終日は、僕から飛び出してやがて独り立ちしてしまった一本の映画が人々とどんなコミュニケーションをとったのかなと思いながら、観客に混じって暗闇の中でスクリーンを見つめる。上映が終わると、たいがい、何人もの人が、「最終回だからきっと来ると思ってた」「三回見たんですよ」「好きな映画です」などと言ってくれる。「いい映画ですね」ではなく「好きです」と言ってもらえるのがなにより嬉しい。そんな帰り道は、「ウチの子どもはどうやらいい友達を持てたようだな」と、その幸せを噛みしめながら、延々と、歩く。
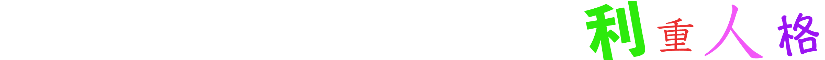
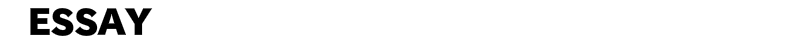
 前のページへ
前のページへ