
旅するように生きたい
三六〇度見渡すかぎりの何もない地平線なんて風景を見たのは、さすがにそれが初めてだった。
テレビの仕事で敦煌からシルクロードを西に向かう途中。ロケバスに揺られながら延々と変わらない真っ平らな風景を見ているうち、ここを撮影しておこうということになった。三十分後にまた来てもらうようにバスを行かせると、道から外れ、ゴビ灘と呼ばれる土漠に足を踏みだす。乾いた表面が足下でぱりんぱりんと音を立てる。カメラクルーの姿が見えなくなるまでしばらく歩いて、辺りをぐるりと一周見回す。見渡すかぎりの真っ平らな荒れ地。遠くが霞んでいるのか、山はおろか、本当になにも見当たらない。以前カンボジアのある小高い丘に登った時、ぐるり三六〇度が地平線という景色が開けて感動したことはあるけれど、その時は眼下にぽつりぽつりとヤシの木や民家が見えていた。それが今度は、シルクロードという一本の道以外、本当に人工物が何も見えない風景なのだ。平らなところに立っているため、いまやその道すらほとんど見えない。一匹の鳥すら飛んでいない。自分以外まったく対象物がない空間。
と、急に異様な感覚に襲われた。自分が今まで生きてきた世界とはまったく別の世界に迷い込んでしまったような、眩暈がするような感覚だった。
風景から感じるだけではないこの異様な感覚は何から来るのだろうと、パニックにも似た気持ちで五感を探る。はっとした。まったく音がないのだった。時折そよぐ風が微かに耳をくすぐる以外、まったくの無音の世界。浮遊しているようでもあり、何かに包まれているようでもあり、畏怖のような、だけどそれとはまた違うこの感覚は、それでだったのかとわかった。
生まれてから今まで感じたことのない感覚を体験するというのはとても嬉しいことだ。何十年も生きてきても、まだ毎年、初めての感覚を体験することができるのだから、まだ感じたことのない感覚というのは途方もなく沢山あるんだろうなと思う。感情もそうだ。嬉しいとか悲しいとか簡単に説明のできない不思議な感情というのはまだまだ沢山あって、そのうちの半分にすらまだ自分は巡り合っていないんだろうなと思う。そう思うとなんだか嬉しい。長く生きていく甲斐がある。
年々自分の感情が鈍っていっているのではないかという不安にふと囚われることがある。日々の生活の中に自分が埋没してしまって、いろんな新鮮な感情を感じるチャンスをずいぶん逃してしまっているのではないかと思ったりする。旅に出ると、自分の細胞のひとつひとつが起きてくるような感じがしてきて、ほんの些細なことでも敏感に反応している自分を感じる。何気ない風景や、すれ違う人の表情をすべて見逃すまいと思う。なんでもない人の優しさが旅先だと心に染みる。
今回の旅でも、人の心が染みた。天産山脈の麓の近くに住むカザフ族のチャンザとビーカンという夫婦を取材しに行った時のこと、個人的なお礼にとポラロイドで夫婦の写真を撮って進呈したところ、チャンザが急に「あ、そうだ」という感じで嫁のビーカンに何か話すと、奥の部屋の壁に貼ってあったカザフ族が結婚する時に必ず必要だという大きな手作りの布を持ってきて、くれると言う。それは大切な物なんじゃないかとびっくりして聞くと、きっともう二度と会えないだろうけど、遠い国から来たお客さんと出会った記念にもらって欲しいとチャンザは言った。その傍でビーカンも垂れ目のおっとりした顔で嬉しそうに笑っている。なんだか急に胸が熱くなった。今さっき知りあったばかりの、流れてきて、ただつまみ食いをしていくような僕らに対してどうしてそんなに優しいのか。そしてその彼らに対して、彼らが喜ぶことなら何でもしてあげたいと思うこの気持ちは何なのか。
旅先でこういう触れ合いがある度に、いつも心をオープンにしておこう、自分も人には親切にしようと、改めて心に誓う。頭でっかちな理屈をこねまわしたり、すぐに不機嫌になったり、変な照れで人と仲良くなるタイミングを逃してしまったり、感謝の気持ちを伝えなかったり、もう、そういう自分はなくしたい。本当にそう思う。この感じを日本に持ち帰り、今度こそ、いつの間にか鈍くなったりしないようにしたい。東京に住んでいても、旅しているときと同じように、周りに起こっているすべての小さいことまできちんと感じて生きてゆきたい。同じ瞬間の同じ景色を二度と見ることは出来ないし、同じ人と一生一緒にいることも出来ない。欲張っても出来ることは決まっている。だからせめて、自分の一瞬一瞬を、どれだけ覚醒させて生きてゆけるか。そのことを欲張りたい。まず自分というものがいて、自分という意識をもっていて、いろんな感情を持っているという永遠の不思議を忘れたくない。
旅をするように生きたい。
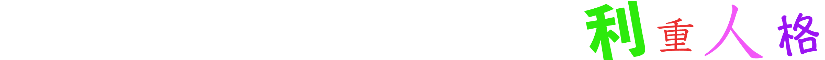
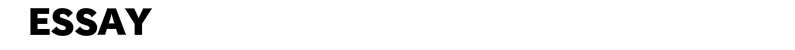
 前のページへ
前のページへ