
緒形拳さんのこと 1
緒形さんと初めて仕事をしたのは、1984年、『羽田浦地図』というNHKの連続ドラマだった。僕がまだ確か21歳の時。
それは、小さな町工場がひしめき合う羽田を舞台にしたドラマで、緒形さん演ずる流れ職人の旋盤工が町に戻ってくることから始まる人間模様で、僕はその中で、学生運動から命からがら逃げてきて、匿ってもらううちにその工場で働き始める若者という役柄だった。
ロケの初日、舞台となる町工場の2階の待機場所で、僕はいきなり緒形さんと2人きりになってしまった。たまたまクランクインが2人とも出ていないシーンだったのだ。
もちろんそれまでに一応挨拶はしていたものの、もう一度ちゃんとしとこうと、「あの、どうぞよろしくお願いします」と頭を下げると、緒形さんは「おう」と短く応えただけで、それきり黙っている。
うわあ、気詰まりだなあと、困った。黙っている身体から発する威圧感というか、オーラというのか、うわあ、ここに緒形拳がいるよぉ、って感じ。それ以上話しかけていいのか、話しかけて欲しくないのかわからない。
それまでも有名な俳優さんとはたくさん仕事していたし、仕事になれば誰が相手でもあまり緊張しない生意気な自分だったけれど、世間話みたいなことはとても苦手だったし、おまけに、生粋の映画青年だった僕は緒形さんのかなりのファンだったので、好きな人にはかえって人見知りしてしまうというか、いろいろ聞きたいこともあるし仲良くなりたいと思うんだけれど、何からどう話しかけていいのか言葉が頭の中にぐるぐるしてしまって、結局長ーい沈黙のみの時間が流れていった。
静かにパニック状態になりながら、ちらりちらりと目の端っこで緒形さんの方を窺うと、化粧台の方をじーっと見ていた緒形さんが、やおらドライヤーを手にして眺めだした。確か〔ドラドラ1000〕とかいう、折りたためるハンディタイプのドライヤー。それを、持ち上げてみたりひっくり返してみたり、ためつすがめつ眺めている。
「おおー、すげえー。ドライヤーを何分間も見てるぜ、オガタケン。いったいなに考えてんだろう?やっぱりすげえ俳優はなんでもじっくり観察するんだろうか?それともまったく別のことを考えてるんだろうか?」と思いながら、じろじろ見ないように観察していると、急に緒形さんが、「おい」と太い声で言った。
「はい、」と内心飛び上がりそうになりながら答えると、緒形さんはこっちにそのドライヤーをゆっくり突き出しながら、「こりぃ」と言った。
(注:緒形さんの「これ」は「こりぃ」に近い感じに聞こえる。ちなみに「俺」は「おりぃ」に聞こえる)
「……なんでしょう」
「こりぃ、掃除機か?」
なんと応えていいか、まったくわからなかった。
冗談なのか? ここは笑ったほうがいいのか。今自分は何かを試されているのか。しかし、もし本気で聞いているとしたら、返しようによっては失礼になるし……とさらにパニックになりながら、ようやくのことで僕は、「……いえ、それはドライヤーだと思います」と慎重に答えた。
すると緒形さんは、無言で俺を見つめ、もう一度ドライヤーを眺め、ゆっくりとそれを化粧台に戻した。表情が変わらなかったため、結局意図がなんだったのかわからず、僕がまだ戸惑っていると、緒形さんは、ごっつい掌でゴシゴシと自分の鎖骨のあたりをこすり、「ちょっと、寒いな」と言った。
「あ、じゃあストーブつけましょう」と、僕が急いでストーブのスイッチの方に手を伸ばすと、緒形さんは「おいっ」と目を見開いて、僕に手を伸ばす。
「はい?」
「気をつけないと、ガスはあぶないぞっ、ガスは」
「……。緒形さん、これ……電気ストーブです」
それは、スイッチをパチンとするとニクロム線が真っ赤になる、誰もが知ってるあの単純な上下2段式の電気ストーブだった。
「……」
にまーっと、なんともいえないあの笑顔がゆっくりと顔いっぱいに広がっていき、緒形さんは、伸ばした手をまたゆっくり戻した。
そして、言った。
「おりぃ。バカだから」
思わず僕は爆笑し、すっかりリラックスして、それから僕らは急に仲良くなったのだった。
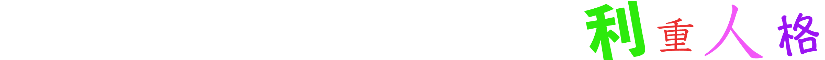
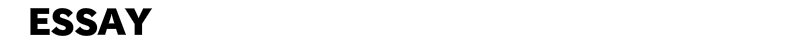
 前のページへ
前のページへ