
飛んでいった風船
娘が3歳になった日。みなとみらいで綿菓子を買ってあげて帰る途中、娘が、あっと小さく声をあげた。
娘の視線の先を追うと、遠くに、風船がひとつ、ビルの谷間を昇っていくのが見えた。そしてその下の舗道には、それを見上げる、娘と同じぐらいの男の子の姿があった。
娘は、その光景がよほど気になったのか、家に帰ってきてからも、「だれのふうせんがとんじゃったの?」と、何度も聞いた。
「きっとあの男の子のだね。知らないおともだちの風船、飛んじゃったね。かわいそうねー」と答えると、今度は、「なんでとんじゃったの?」と聞く。
「ちゃんと手にぐるぐる巻きつけてなくて、するっ、てすべっちゃったのかな」
「なんで」
「うーん。手が小さいから上手に持てなかったのかな。でも、おかあさんにもうひとつ買ってもらったかもしれないね」
娘はウンと頷き、やがてひとりで遊びだしたが、しばらくするとまた、ふと、「だれのふうせんがとんじゃったの?」と聞く。
「飛ばしてみたかったのかもね」
「なんで」
「わからないけど。手を離したらどうなるか知りたかったのかもしれない」
「なんで」
「わかんない。でも、やってみたかったのかもしれない。どこまで飛んでいくのか見たかったのかもしれない。でも、ホントにお空に飛んでっちゃったら、もう取れないってわかって、あ~あって思ったかもね」
そう答えると、娘はちょっとの間考えてから、またウンと頷いたが、しばらくするとやっぱりまた同じ質問をする。
今度は嫁さんが、「また誰かのおともだちのところに、こんにちはって降りてくるかもね」と答えると、またウンと頷くが、しばらくするとまた質問。その一瞬の光景は娘の心によほど強い印象を残したようで、なにをしていても彼女のどこかにずっとひっかかり続けているようだ。
と、何回めかの質問を繰り返した後、突然娘は、「じゃ、のんちゃんが取ってあげるよ!」と、驚くほど大きな声で言った。
ずっと考えていたことを思い切って宣言したようなその言い方に、こちらも何か感じるものがあって、思わず「ホント?じゃ、取ってあげて」と言うと、娘は、「ウン!」と、力の限りジャンプをして、架空の風船を取って、こちらに渡してくれる。すかさず小さな男の子の役になって「わー、ありがとう」と言うと、娘の顔がぱっと輝いた。
これだ!と思ったのか、娘はそれからずっとそのシーンを繰り返した。
「えーん、えーん、て泣いて」
「えーん、えーん」
「じゃ、のんちゃんが取ってあげる!」
「ありがとう!」
延々と、この繰り返し。だけどきっと、自分の気がおさまるまで繰り返す必要が娘の中にあるのだろうと思い、徹底的につきあうことにした。彼女は、たとえそれがおままごとであっても、可哀想な出来事を自分が助けてあげて、自分を納得させたいのだと思う。風船をなくしてしまった子の悲しみを、まるで自分のことのように想像し、でも何もしてあげられない自分がもどかしくて、彼女はどうしてよいかわからずに、ずっとあの質問を繰り返していたのだと思う。たとえ想像の世界でも、男の子のために風船を取り返してあげたかったのだと思う。優しいな、と胸が熱くなる。
こういうおままごとに延々とつきあったり、同じ絵本をリクエストされるままに何度も読んであげる時、変な話だけど、役者をやっていてよかったなと思う。だって、同じ台詞を何度も繰り返すのなんて、全然平気だもの。仕事のことを考えれば、なんてことない。何度も繰り返し求めてくれて、そのたびに心を動かしてくれる人が目の前にいるなんて、これ以上の冥利はない。それで彼女の心の泡立ちがおさまるのなら、テイク30や50ぐらい、いくらでもつきあってあげようと、思える。
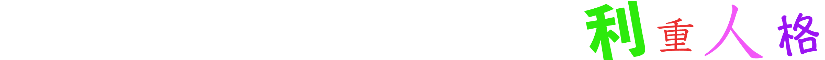

 前のページへ
前のページへ